ZEBにはメリットがたくさん。ZEHの違いや達成までの段階も解説
日本では2050年にカーボンニュートラル達成を目指すという方針を打ち出しています。
そのため、建築業界ではZEB化への取り組みが強化されており、
理想論ではなく皆が自分ごととして本気で取り組まなければならないところまできています。
ZEB化は企業の経営に大きく関係することもあり、関心を持っている事業者も多いかもしれません。
そこで今回はZEBの概要やZEHとの違い、ZEBのメリットなどをまとめていきます。
関心のある方や、何から始めればよいかわからない方もぜひ参考にしてみてください。
ZEBとは「一次エネルギー消費量ゼロ
の実現を目指す建築物」
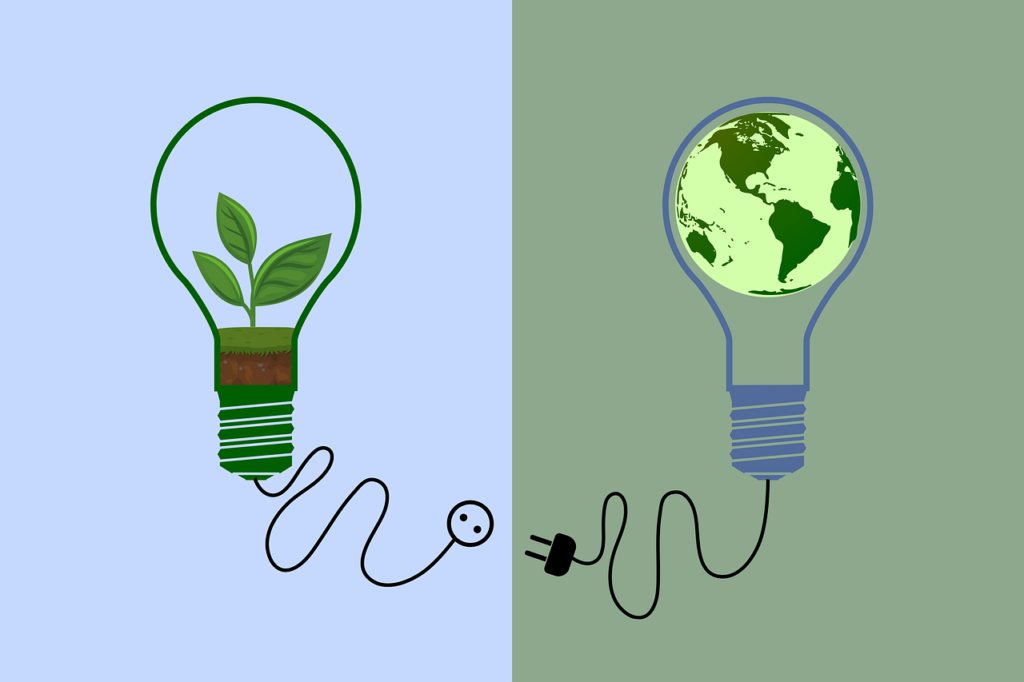
ZEB(読み方:ゼブ、正式名称:Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル))とは、エネルギー収支ゼロの実現に向けた建築物です。
一次エネルギー消費量の削減とエネルギーの創出ができる建築物を目指します。
(※一次エネルギーとは:
加工せずにそのまま使用できるエネルギーです。
例として石油、石炭、天然ガス、水力、太陽熱、地熱などがあります。
また、一次エネルギーをもとにつくられるのが二次エネルギーです。
例として電力や都市ガスなどがあります。
生活の中で私たちは二次エネルギーを使います。
しかし、建物の消費エネルギーを計算する際には元となる一次エネルギーに換算することになっています。)
2030年に新築される建築物はZEB基準の省エネルギー性能の確保を目指すなどのロードマップが国により作成されています。
ZEB化は新築はもちろん、改修によって実現することも可能です。
具体的な方法は建築物によります。
ZEB化した事例を参考までに知りたい場合には、インターネットで検索すると見つけることができます。
さらに詳しく知りたい場合には、一級建築士事務所等に問い合わせてみるとニーズに沿った情報を得やすいでしょう。
ZEHとは?
ZEBとの違いは?
ZEBはビルや病院、工場などの大規模な建築物を、ZEHは住宅を対象としている点に違いがあります。
ZEH(読み方:ゼッチ、正式名称:net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、エネルギー収支ゼロ以下を目指す住宅のことです。
ZEH化に向けて性能を向上させると、例えば住居内の寒暖差で生じるヒートショックのリスク軽減などのメリットがあります。
新築住宅について2025年4月以降は省エネ基準の適合が、2030年はZEH基準の適合が義務化される予定です。
ZEBは4段階ある

経済産業省資源エネルギー庁は、ZEBについて以下の通り4つの基準を定めています。
| 建築物の条件 | |
| ZEB | ・省エネで50%以上のエネルギー消費量の削減 ・創エネも含めて100%以上のエネルギー消費量の削減 |
| Nearly ZEB | ・省エネで50%以上のエネルギー消費量の削減 ・創エネも含めて75%以上100%未満のエネルギー消費量の削減 |
| ZEB Ready | ・省エネで50%以上のエネルギー消費量の削減 |
| ZEB Oriented | ・事務所、学校、工場等:省エネで40%以上のエネルギー消費量の削減 ホテル、病院、百貨店、飲食店、集会所等:省エネで30%以上のエネルギー消費量の削減 ・未評価技術(WEBPROで評価されていない技術)の導入 |
基準が最も厳しいZEBを達成することが本来は理想的です。
しかし、いきなりZEBを目指すことが難しい場合も当然考えられます。
その場合、まずは省エネに力を入れてZEB OrientedやZEB Readyの基準を満たすという方向性もありでしょう。
その後の改修の際などに創エネができる手法を取り入れることで、段階を経てZEB化を達成することも可能です。
ZEB化は建築主や
建物の利用者のメリットも多い

ZEBは事業者などの建築主や、利用者にも実はたくさんのメリットがあります。
ここではその一部を紹介します。
光熱費の減少
ZEB化をすることで光熱費を節約できます。
環境省によると、延床面積10,000㎡程度の事務所ビルの場合40%〜50%程度の光熱費の削減につながる可能性が示されています。
オーナーは共有部分の経費などを、テナントは毎月の運営に関わる経費などを削減できるでしょう。
経済的なメリットを享受できる場合にはより積極的に取り組みやすいという方も多いかと思います。
設計手法によってはランニングコストをしっかり削減しながらZEB化を進めることは十分可能です。
BCP対策の強化
ZEB化はBCP(事業継続計画)と合わせて進められます。
例えば創エネ性能を高めることで、災害時等における事業継続を可能にします。
有事の際に困らないことはもちろん、取引業者やお客様などの関係者へ安心感を与えることにもつながるでしょう。
また防災拠点として開放することを想定して建築するなど、地域に密着した取り組みも注目されています。
ZEB化はBCP対策はもちろん、関係者や地域住民とのつながりを強くするきっかけにもなります。
快適性や生産性の向上
建築物の断熱や遮熱性能を高めることで、より快適な室内環境をつくることが可能です。
例えば太陽光などの自然エネルギーを積極的に活用することで、建物内の寒暖差が減りより心地よく過ごせます。
労働環境が重視される昨今では、特にオフィスビル内の快適性を高めることはオーナーや企業にますます求められていくのではないでしょうか。
オフィスに限らず健康を守れたりパフォーマンスを高めたりできる建築物は世間のニーズにも合っているといえるでしょう。
何から始めればよいか分からない方も、
まずはご相談ください
ZEBについてなんとなく興味が湧いているものの、
「具体的にどのような方法があるの?」
「改修のついでにZEB化も検討してみたい」
などの疑問や悩みをお持ちの方も多いかもしれません。
何から手をつければいいのか分からない方も、スギウラ・アーキテクツまでぜひ一度ご相談ください。
ZEB化に向けた最適な方法はケースバイケースであるため、既存の建物や面積などに応じた方針を検討します。
ZEB化には初期費用がある程度かかることも踏まえて補助金の活用も視野に入れて進めていきます。
ZEB化はランニングコストの削減や快適な日常にもつながる手法であるにもかかわらず、導入ハードルを感じてしまうのは非常に勿体無いことです。
また一人ひとりが本気で考えていかなければ、国の目標を達成するのはなかなか難しいと感じます。
弊社は一級建築士事務所として、お悩みや疑問をお持ちの方のサポートをしていきたいと考えています。
目先の問題だけを解決するのではなく、人や企業、社会が幸せを長期にわたって感じられる設計技術を提供いたします。
ご興味のある方はまずはお気軽にご相談ください。